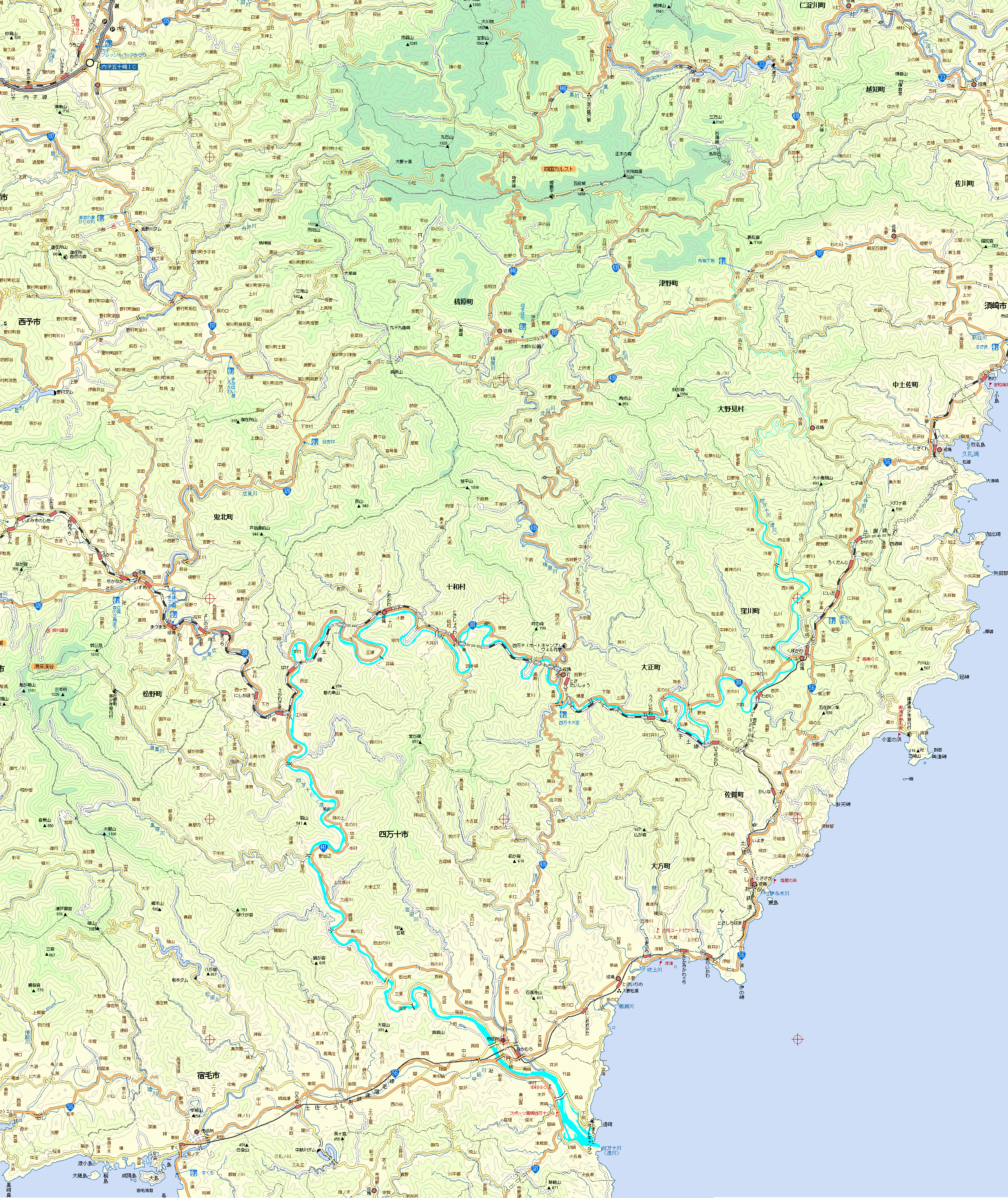
だるい人はちっちゃいマップ見るといいよ
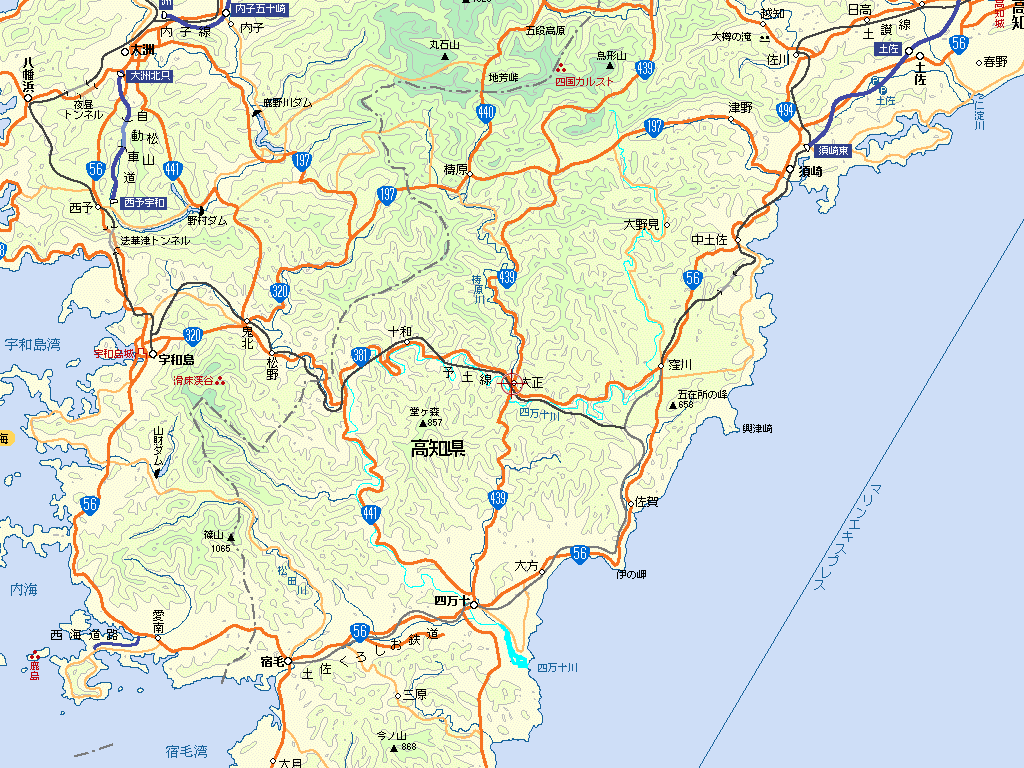
まあ、おれも行くまで全然しらねかったんだけどもね、
地理とか義務教育以上の勉強してないしね
<日本の代表的な河川>
日本最長。長野県内では千曲川。実は「千曲川」と呼ばれているところのほうが長い。 流域面積が日本最大。
信濃川
367㌔
長野と山梨の県境から発し、八ヶ岳のふもとを流れて長野を縦断、新潟県にはいると信濃川と名を変えて新潟市で日本海へ
利根川
322㌔
群馬県の奥、尾瀬より発し、前橋を経由、埼玉をかすめて茨城にイン、茨城と千葉の県境となって銚子で太平洋に注ぐ。
石狩川
268㌔
長さ3位、流域面積2位
大雪山から旭川を経て滝川、江別を通り札幌の北で日本海・石狩湾に
天塩川
256㌔
旭川の北約20キロの塩狩峠に発し、
ひたすら北上、名寄、音威子府を経て幌延で日本海へ。
北上川
249㌔
岩手県北部から南下、
盛岡、花巻、水沢、平泉を経て、仙台の北で太平洋に注ぐ。
阿武隈川
239㌔
福島県南部の白河から福島県内を北上し、
郡山、福島を抜け仙台の南で太平洋へ。
最上川
229㌔
山形県最南部から山形県内を縦断し、
米沢、寒河江、新庄を経由して酒田で日本海へ。
木曽川
227㌔
長野県木曽福島から中津川、恵那を通り、
大きく西に蛇行して岐阜県を横断、岐阜市南部で南進して名古屋の西で伊勢湾へ。
天竜川
213㌔
長野県諏訪湖から中央アルプスと南アルプスの谷を抜け、
真直ぐ南へ、浜松で太平洋に注ぐ。
阿賀野川
210㌔
奥会津に発した阿賀川が、
尾瀬・只見湖・猪苗代湖などからの支流を集めて会津で阿賀野川となり、新潟北部で日本海へ
四万十川
196㌔
本件
江の川
194㌔
中国地方最長。
中国山中芸北から発し、三次から島根に入り、島根県中央の江津市で日本海へ。
吉野川
194㌔
愛媛県と高知県の県境、石鎚山付近より発し、
北土佐から大歩危・小歩危を抜けて池田へ、徳島県を横断して徳島市で太平洋・紀伊水道へ
熊野川
183㌔
近畿最長。
奈良県深部に発した十津川が和歌山県で熊野川と名を変えて太平洋へ注ぐ。
荒川
174㌔
埼玉・山梨県境の甲武信岳から秩父を抜け、埼玉から東京を縦断して葛飾を経て東京湾へ。
筑後川
145㌔
阿蘇北部の九重山から、大分・福岡県から久留米を抜けて有明海へ
多摩川
138㌔
奥多摩湖から青梅、立川など武蔵野丘陵をぬけて、東京と神奈川の県境となって川崎で東京湾へ
九頭竜川
118㌔
福井県深部の両白山地から福井市内をぬけて日本海へ。
球磨川
115㌔
熊本県南部の湯山から人吉を経て八代で八代海へ
豊平川
76㌔
札幌シティを流れる川。石狩川の支流。
淀川
75㌔
大阪民が必死な川。宇治川・木津川・桂川が合流して淀川に。
こうやって眺めてもらうと、源流が著名な山っていう川がほとんど無い。
なぜかちゅうと、有名な高い山から流れ出ると、流れが急になって、あっという間に海に出てしまうもんで、長くなれないからだべ。
逆に、長い川はほとんど無名な山地から発していて、ゆるやかに蛇行することで距離を稼いでいる。
山が険しい日本には、大陸のような「大河」は存在しない。
どの川も、ミシシッピやナイル、ラインやドナウに比べると急流だ。
さて、そこで四万十川だが、冒頭の地図を見ていただけるとわかるが、「四国カルスト」の南部で発した川は、
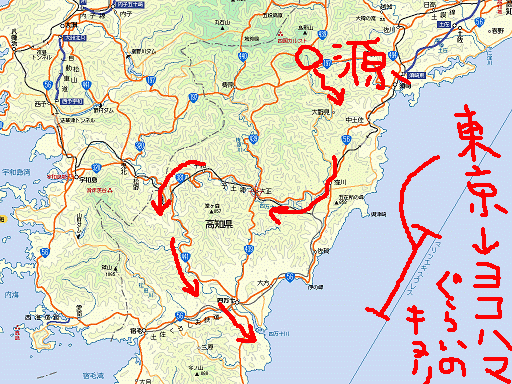
南下して窪川付近で黒潮にちかづくが、そこからぐねーーーーーーっと大きく北西に転回し、
大正で梼原川、ハゲで広見川を束ね、河口の手前で後川と合流して中村市(現四万十市)で土佐の黒潮に注いでいる。
実は、この四万十川の全長196㌔のうちの後半100㌔は、高低差が約200㍍しかなく、ほとんど真っ平ら。
勾配で言うと2‰だ。パーミルなんて鉄ヲタにしか通じないね。
もうちょっとわかりやすくいうと、1㌔で2㍍、100㍍で20㌢、10㍍で2㌢、1メートル流れる間の高低差が僅か2㍉だ。
これは平らだ。
なにしろバリアフリー住宅の定義が、段差が3ミリ以内だ。

四万十川はバリアフリー住宅よりバリアフリーなのだ!!
この平らさゆえに、長さこそ諸大陸の大河の数千分の一だが、流れのふいんき(何故か変換できない)は大陸並。
日本にはそういう川はあんまりないようだ。
それに、こんだけ平らだと、ダムとか作れないんだ。

だから、四万十川にはダムが作られずに、その結果、自然が守られて、いまや「日本最後の清流」と呼ばれるまでになった。

って、源流まで遡ったあとで知りました。